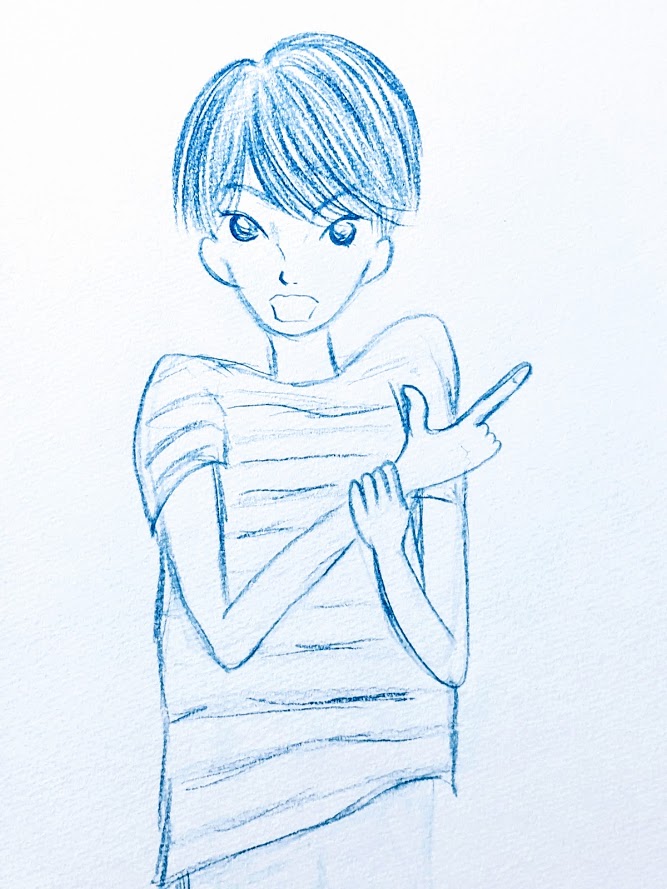10 第二夜
遠い道のり、歩いてきたから、疲れているはずなのに、眠れない。
シャワーを浴びて、スイカを食べて、豆大福もひとついただき、ふとんを敷いた。
時計が、ボーンと時刻を告げる。
ボーン、ボーンと八つ鳴る。
「さあ、早く寝なくっちゃ」
って、いやいやいやいや、まだ8時だよ、子どもじゃ、あるまいし。
記憶にあるのは、自分にそう突っ込みを入れたところまで。
その後、ぱたんと眠りに落ちた。
どうもそういうことらしい。
そして、目覚めると、
ボーン、ボーン、・・・ボーン
時計が、10個、時を打った。
「お腹、へった」
スイカと豆大福だけじゃ、あたしのお腹は、朝までもたないらしい。
策作じいさんを起こさないように、忍び足で台所へ。
台所は、闇に包まれている。
電気は、電気のスイッチはどこだ?
と、目を凝らした時だった。
なんだ?
闇の中、動く光は、懐中電灯のようだ。
焦るな来月、これは、どういう状況だ?
泥棒? 強盗? 痴漢? 変態?
いやいやいやいや、焦るな、来月。
もしかしたら、賢作さんかもしれないし。
って、いやいや、それは、ありえない!
停電の時ならいざしらず、自分の家で、懐中電灯、使わないだろ?
それに、あたしの使わせてもらってる客間には、ちゃんと電気は点ってる。よって、停電でないことは明らかだ。
ならば、あの、怪しい影は、泥棒!
泥棒ならば、強盗に変身することだってあるはずだから、いや、ドラマの世界では、お決まりの設定だ、だから、だから、下手な手出しはしてはいけない、110番だ! と、頭では、わかっているのに、この口が、勝手に叫ぶ。
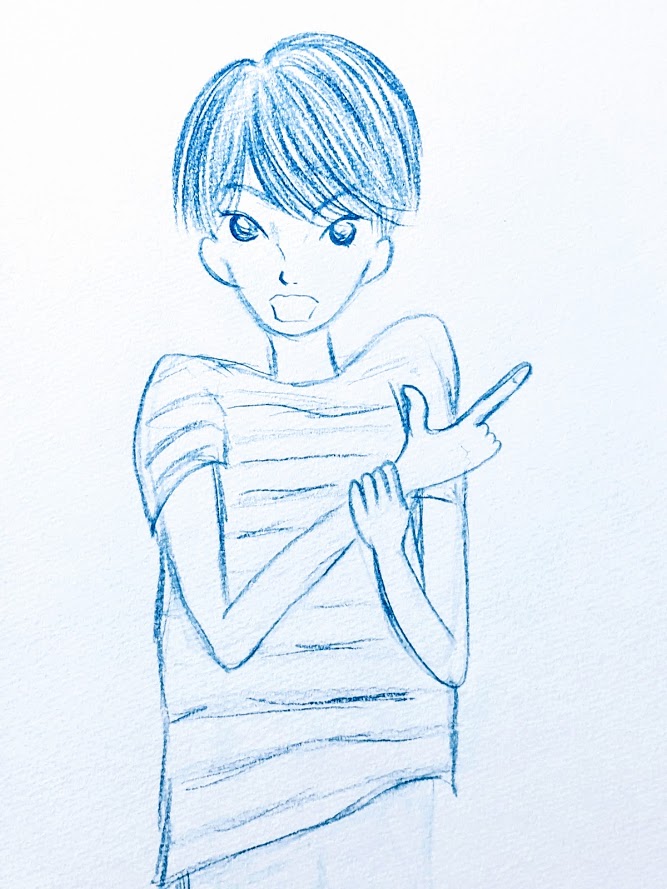
「手を上げろ! そして、武器は捨てなさい!」
「その声は、安達ケ原さん?」
というその声は、佐熊山賢作さん!
「台所の電気が切れちゃって。この懐中電灯、持っててくれる?」
「はい・・・」
あたしは、あたしは、あたしは、アホだ。