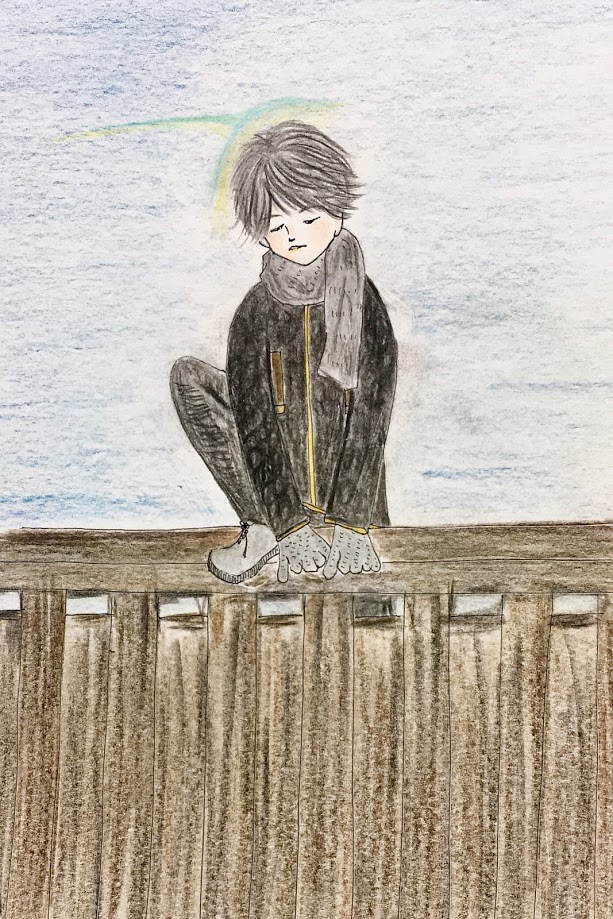4 出動
「それより、アキラ、丹田さんの猫捜しの件、そろそろ出動した方がよくはないか? な、とりあえず、チャッピーの件は、忘れて」
「忘れません!」
「では、とりあえず、あっちに置いて」
「まあ、それなら・・・」
依頼主宅訪問へ、心が動き出す。
「この通りは信号が多いから、車で、15分くらいだな」
猿神さんは、地図を指さす。
「車、あるんですか?」
「ある。キャロちゃんという」
ひっ、車にも名前つけているのか?
「じゃあ、ナビに入力すれば、地図は必要ないんじゃないですか?」
「初めて訪ねる所だぞ!」
「だから、ナビを頼るんじゃないですか」
「いいか、アキラ、ナビは、信用できん。奴らは、はい、ここが目的地です、ときっぱりとした意見を言わない。目的地周辺ですから、注意しろ、と言うだけだ。注意したって、見過ごすのがおちだ。そんな軟弱な機械にワシは頼るつもりはない。第一、ワシのキャロちゃんにはナビなんぞ付けておらんし」
「はぁ。それにしては、お詳しいことで」
「黒岩の車には、付いている!」
きっぱりと宣言するのを聞いて、オレは、見知らぬ黒岩さんが気の毒になってきた。
いろいろと、こき使われているんだろうな。