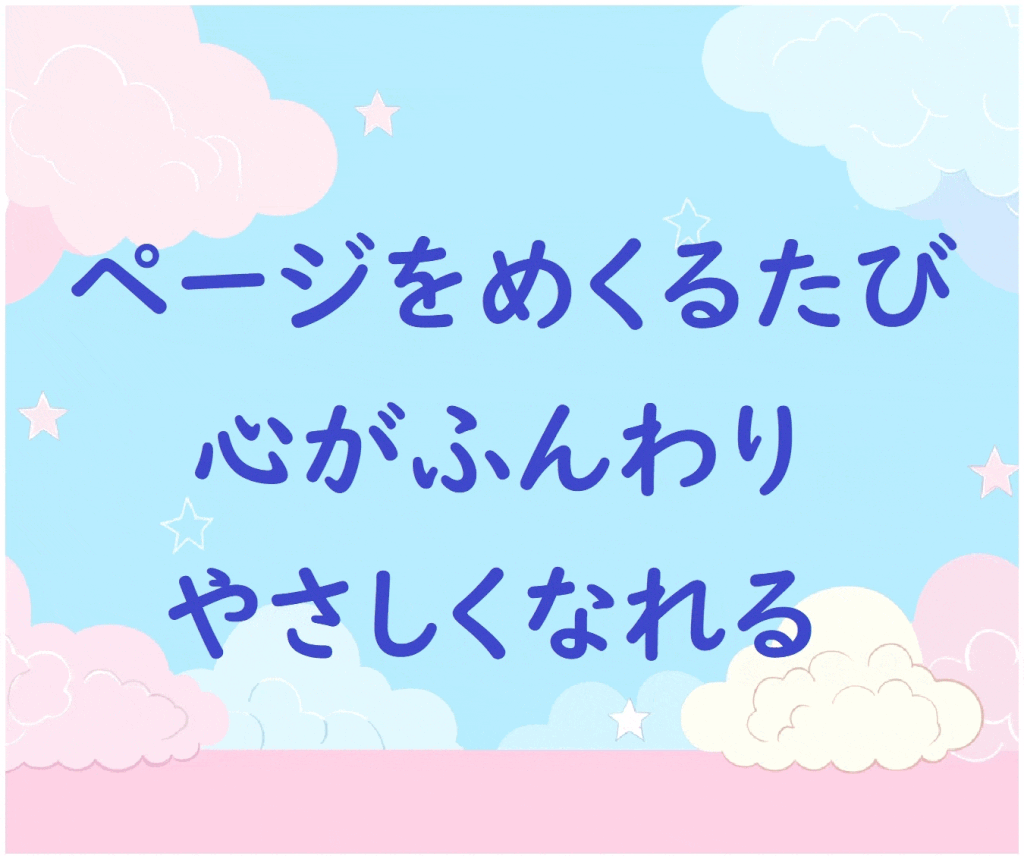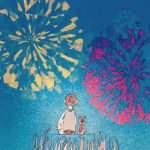「それはいけません、王女さま。ご身分が違いすぎます、あの男とは」
どんなに言い聞かせても、アウロラの決心は変わりません。
「仕方がない。だれぞ、行って、あの若者をここへつれてまいれ」
大臣たちの命令で、農夫の息子ハンスがお城につれてこられました。
びっくりしたのはハンスです。何しろ、いきなり、王女さまのお婿になれの、王さまになれのと言われたのですから。
「お、おら、そんなことはできねえだよ。おとっつぁんから野良仕事は習ったが、王さまの仕事は習っちゃいねえだ」
「王女さまのご命令ぞ。従わぬならば、首をはねるまでじゃ」
大臣たちに脅され、すっかり、縮こまっているハンスに、アウロラはやさしく言葉をかけました。
「私は、ずっと、この部屋で、ひとりぼっちで暮らしてきました。知る世界といったら、窓から見えるものばかり。でも、ちっとも、退屈ではなかったわ。ここから見える景色が、とても好きだったから。青い空。遠い雲。緑の森に光る川。季節ごとの空気のにおいや、野良で生き生きと働く人々の姿。でも、何より楽しみだったのは、ハンス、おまえを見ていることでした」

「おらを見てただって!」
ハンスは、思わず、窓にかけ寄りました。なるほど、そこからなら、城壁の向こう、広々とした野良だって見渡せたのです。
「あれま。ほんとだ。おらんとこの畑がまる見えだ!」
「おまえは、最初、小さな泣き虫こぞうでした。母さまのスカートにすがって、なかなか離れず、仕事のじゃまばかりしていたわね」
「おらの鼻水まで見えただかね」
ハンスは顔を赤らめました。
「そのうち、少しずつ、きょうだいの面倒をみたり、種をまいたりして、親の手伝いをするようになりました。そして、今は、鉄のすきをたくましい馬に引かせて、広い畑をひとりで耕すまでになった。そんなおまえを、いつの頃からか、私は自分の夫にと決めていたのです」