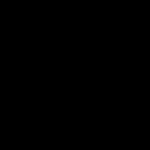この日以来、オレは土曜日の午後になると、新宿東口の電話四郎のところに立ちよるようになった。
四郎と話せるのは、タイミングがある。ランプが消えているときだ。
四郎はオレの姿を見つけると、ランプを消してくれる。そうすると、「この電話は使えない」と思って、だれも四郎に近づかないからだ。
といってもケータイやスマホを持っている人が多いので、四郎を使おうという人はほとんどいないのだが。
「オレな、大阪に好きな子がいるんや。ときどき電話で話すんやけど、今年は中学受験やろ。これからどうしたらええんかなあ」
「ラブレターを毎日書くのはどうや、幸平くん」
「手紙か? 古くさいな。今やメールとかラインの時代やで」
こんな具合に、オレは四郎とその日の学校のこと、家族のこと、彼女のことまで話すようになった。
四郎のおかげで、オレは毎日とても元気になった。学校でも塾でも、クラスメートと話がうまくできるようになってきた。
こんなすごい電話があることを、ひとりじめにしてはもったいないと、オレは塾でとなりの席の佐藤くんに話してみた。佐藤くんはオレと同じようにお父さんの仕事の都合で宮城県から引っ越してきたばかり。ちょっと引っ込み思案だ。
「東京の友だちとは話があわねなあ。四郎さん、オレは国にさ、けえりてえんだ」
「もうすこす、しんぼうしてみさい。佐藤くん」
翌日、佐藤くんは明るい表情で塾に来た。
「幸平君。ぼく、すごくすっきりしたよ。また四郎くんのところに電話しにいくつもりだ」
佐藤くんは、2年下の妹のユリちゃんに、四郎のことを話した。ユリちゃんは、家庭教師で宮崎出身の西先生に話した。西先生は、友だちで沖縄出身の花城さんに、という具合に四郎のことが口コミでどんどん広まっていった。
 いつの間にか新宿東口の緑の公衆電話は、お国ことばで悩みの相談にのってくれると評判になった。いつ行っても、だれかが四郎と話している。
いつの間にか新宿東口の緑の公衆電話は、お国ことばで悩みの相談にのってくれると評判になった。いつ行っても、だれかが四郎と話している。
ある日の夕方、四郎のところにいってみると、なんと行列ができている。女子高生に、中年サラリーマン、そして小学生まで・・・十数人が四郎の電話の順番を待っている。まるで人気占い師のようだ。
少し離れてオレは、しばらく様子を見ていた。
「ありがとう、四郎くん。私、明日からがんばって学校に行ってみる」
それまでうなだれて受話器をにぎっていた女子高生に笑顔がもどった。どうやら学校でいじめにあっていたみたいだ。彼女はせすじをのばし、元気よく改札口の方に歩いていった。
同じように、疲れた中年のサラリーマンも、不安げな小学生も、電話のあとすっきりとした顔で四郎のもとをはなれていった。
「四郎のやつ、すごいで。もう地方出身者だけやなくて、大人も子どもも、どこの人にもみんな元気を分けているんや」
オレは飛び上がらんばかりだった。そして四郎をみいだして、四郎のことをみんなに紹介できたことに鼻高々だった。