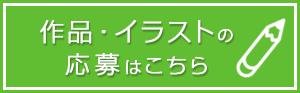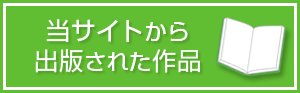読者対象に合わせた書き方を
この後も、だれはこうした、それでどうなった、だれがこう言った、ああ言った、という叙述が続いて、軽快なテンポで話が進んでいきます。
心理描写もシンプルです。
きつねの こは、はやくちで そう いいました。(P12)
きつねの こが さけぶように いいました。(P30)
どしゃぶりの あめの したで、ぬれた ばけつを みていると、きつねの こは、なんだか なきたくなってきました。(P46)
といった感じで、大事な場面にひと言ずつ入れてあるだけです。これで、幼年の読者はきつねくんの気持ちがちゃんと読み取れます。いや、これだからこそ、きつねくんの気持ちがくっきりと浮かび上がってきて、よくわかるんですね。
題材選びだけでなく、読者対象に合わせた書き方をしなければならないというのも、大人の文学にはない子どもの文学の難しさだと思います。

★野村一秋先生のインタビュー記事もぜひご一読を!
『ミルクが、にゅういんしたって?』著者・野村一秋先生に聞く(1/3)
→ https://x.gd/etXKc
『ミルクが、にゅういんしたって?』著者・野村一秋先生に聞く(2/3)
→ https://x.gd/oTLHR
『ミルクが、にゅういんしたって?』著者・野村一秋先生に聞く(3/3)
→ https://x.gd/sq5xe