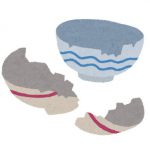ゴチン!!
ゴチン!!
べにちゃんのぐーの手が、ぼくのアタマに落っこちた。その一撃は朝から夢遊病に取りつかれ、向こう側にいたぼくを、いっぺんにこちら側へ引き戻した。いとも簡単に。
「とにかく早く帰るわよ、おばさん、泣きながら警察に連絡する、警察に連絡するって、すごく心配してるんだから!ほら、早くしないと本当に警察がきて怒られちゃうわよ」
「・・・うん」
ぼくは、恐る恐るゆっくりと、べにちゃんの顔を見た。
べにちゃんは怒っているようにも、悲しんでいるようにも見えなかった。・・・少しだけ安心した。
ただ、ぼくはべにちゃんの顔を見るのが、すごく久しぶりな気がした。年という単位。1年とか3年ぶりにべにちゃんと再会したように思われた。
ぼくはうれしくなった。だって、何年かぶりに会えたのだもの、嬉しくないはずはないのだ。
「・・・ありがとう、べにちゃん、ぼくを見つけてくれて」
べにちゃんでなければならなかった。べにちゃん以外の人だったら、ぼくは朝からつづいた夢遊病から覚めることは、なかっただろう。
そしてわかった。
ああ、やっぱりこっちだ。片恋でも、たとえ嫌われたとしても、べにちゃんのいるこの世界の方が、だんぜんいい。