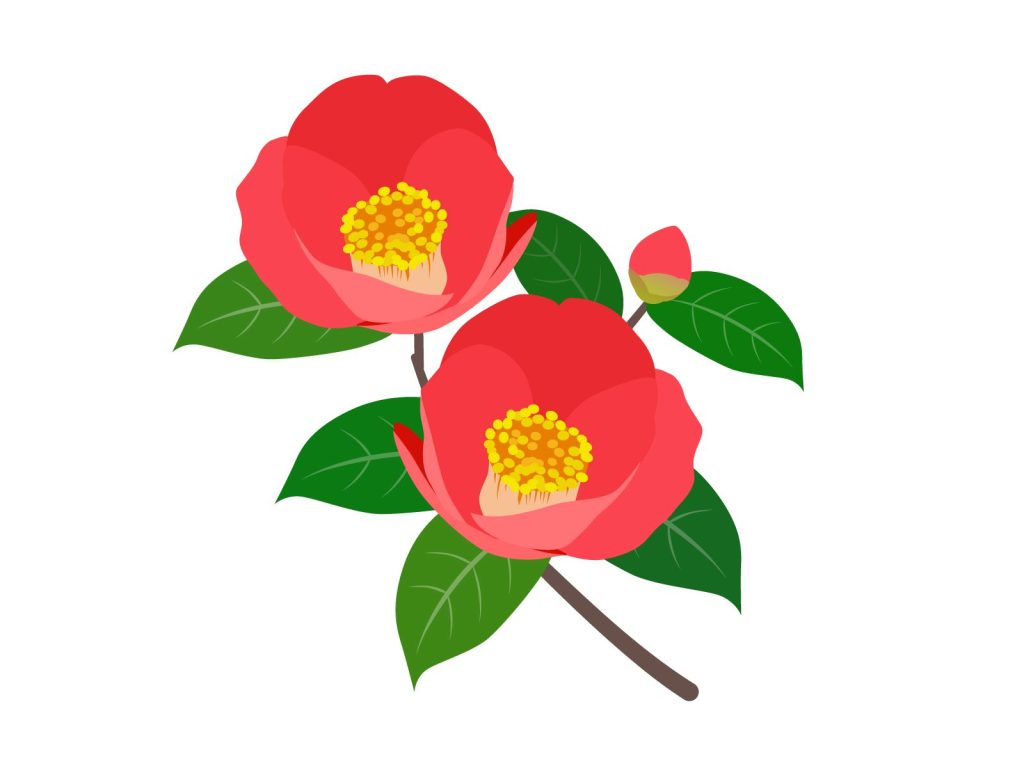おねえさんは、うなずきながら、
「お茶は、のどのかわきをいやすだけじゃなく、声のない会話なの。心をこめてお茶をいれると、飲んだ人もありがとうと返してくれる。声がなくても想いは伝わるものよ」
茶わんを片づけた二人は、なかよく立ち上がり、茶室の戸を開け放した。外はもうすっかり明るく、新年のまぶしい光がさしこんできた。
おねえさんと別れて、家へもどると、おばあちゃんが心配そうに玄関に立っていた。
「どこへ行ってたの? 探したのよ」
「あのね、大福茶を飲んだの。お茶のじょうずなおねえさんが、たててくれたの」
「あらあら、お客様だったの? えっ、『雪後庵』は鍵をかけていたはずよ」
びっくりして、おばあちゃんと見に行くと、確かに門に鍵がかかっている。
「鈴ちゃんったら、寝ぼけてたのね」
「ちがうもん! 見たもん。えっと、おねえさんと掛け軸(かけじく)だって、かけたもん。『天下梅花生』(てんかばいかをしょうず)って書いてあって、意味を教えてもらったよ」
ところが、中に入ると、巻いたままの掛け軸が床の間(とこのま)に置いてあった。
「うそじゃないもん」
泣きべそをかく鈴を、おばあちゃんがなぐさめる。
「だれだって、夢は見るものよ。お茶の夢なんて、すてきだわ。・・・おや?」
おばあちゃんは、床の間の柱に飾った花入(はないれ)に目をとめ、首をかしげた。
「おかしいわねぇ。お正月用に美しい白玉椿をさしておいたのに。柳だけしかないわ」
鈴は、その言葉で気づいた。おねえさんのあまい香り、あれは椿の香りだって。
(おわり)