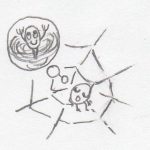くるみは真っ青になって、かくれているのもわすれて、ドアを大きく開き飛び出した。
「ねえ、どういうことっ! ソラはもうウチの犬になったんじゃないの?」
「くるみ! お前、立ち聞きしていたのか。おぎょうぎが悪いぞ」
お父さんはおどろいてくるみをしかったが、くるみにはそれどころではなかった。
「ごめん。でもっ、ねえっ、ソラは?」
「くるみ、あなたはソラのこと、好きじゃないんでしょう?」
こまったようにお母さんがいうので、くるみはあわてた。くるみはソラを好きじゃないことにしているけれど、ソラはくるみのことが好きだ。ソラがまた家族と別れる悲しい思いをするのではと思うと、いてもたってもいられなかった。ソラは、初めて家に来たあの日、あんなに心細そうな顔をしていたのに。
「そうだけどっ、お母さんはソラが好きでしょ? お父さんもそうだし、だったらいいじゃない!」
くるみが食い下がると、ふたりはこまりきった様子で顔を見合わせた。しばらくすると、お父さんはしんけんな顔でくるみに話しだした。
「ソラが、お前のことを好きだってアピールしてるのは、わかってるか?」
くるみは、うしろめたい気持ちで口をつぐむ。ソラに「ごめん」と思う気持ちは、くるみの中にもいつもあったからだ。
「・・・・・・」
「犬は、ムシされるのを悲しいと感じる生き物だよ。今のわが家はあまりソラにとって良くないかんきょうだろうと、お父さんは思っている」
「それは・・・」