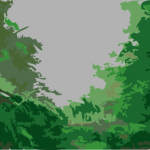ぼくはすべてをあきらめそうになっていた。
けっきょくがんばってもいいことなんてなかった。
始めからほかのなかまといっしょに、もんくをいわずねばらずおとなしくほのちゃんに食べてもらえばよかったのかもしれない。
「助けて」「助けて」
くらい気もちにしずんでいるぼくに、どこからか声がした。
自分の心の声?
いやちがう、だれかがじっさいにさけんでいるんだ。
耳をすますと、森のあちこちから声がする。
大きな木の上に虫たちがいるのを見つけた。
みんなしくしく泣いている。ぼくは木の根元につかまって船をおり、みきをよじのぼった。
「どうしたの?」
昼間会ったミノムシが、おそろしそうに下を見ながらいった。
「かぞくやなかまがおぼれているのよ。前の大雨の時もたくさんの虫たちが命をおとしたわ。またあの時みたいに」
目をこらすと、水にながされている虫たちがいた。
イモムシやアリもいる。どうすることもできずに水の中でもがいていた。
みんなの泣いている顔や苦しそうな顔を見ているうちに、なくなりかけていた「ねばり」の心がぼくの中にまたむくむくと生まれてくるのをかんじた。