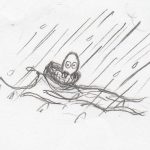ダヴィデはトイレに飛びこみ、はでにゲーゲーやりだした。想像はしていたけど、やっぱりネコと人間の食べるものは完全にちがうらしいのだ。やがて彼はまたワインを一気に飲みくだした。電灯を消し、ベッドにもぐってテレビを見ていたけど、5分もたたないあいだに軽いいびきをかきはじめた。
まんぷくしてやっとおちつきをとりもどしたぼくは、部屋のすみっこにうずくまった。冷たいタイルがいごこちわるい。部屋のどこにいってもさむそうだ。ステッラの家でこんなさむい思いをしたことはなかった。ぼくはいつも夫婦のベッドのかけ布団のうえでねていたけど、二人の体温がほんわかこっちにつたわって来て朝まで気持ちよくじゅくすいできたのだ。
こんな所で正月まですごしたら、きっと肺炎になって死んでしまうだろう。ダヴィデだっていっぱいきこんでベッドに入っているのだ。すり切れた皮ジャンを脱いで,その上にタオル地のガウンをきこんでベッド入りなのである。
ぼくはむっくりと起きあがると、そっとベッドにはいあがり、ダヴィデの顔にはなをちかづけた。つけっぱなしのテレビとわずかにさし込む青い光で見るダヴィデの顔はつかれ切っている。まばらなぶしょうひげのやせた顔はそうはくで幼く、悪党のきざしなどまるでない。だのに、人間って起きているときは、どうしてみんな悪人になるんだろう。あわれなダヴィデもネコとおなじように、寝ているときがいちばん幸せでいい子になるんだろう、きっと。
ぼくはおそるおそる彼の足もとにまるくなった。そしていつのまにか布団の中にまぎれ込んでしまったようだ。とっても寒かったからだ。
電話がなっている。瞬間ぼくはゆかにたたき付つけられた。
「この野郎!ベッドにもぐりこんできやがって!」
ダヴィデはおじ気づいたようにさけんでいた。
「枕だと思って抱いてたら!気持ィわるい。しっ、しっ、オレの目のとどかないところにとっとと消えうせろ!」
 ・・・そうなのだ。ふとんの中でぼくは無意識に少しずつ上へ上へとのぼっていったらしいのだ。あたたかい手が僕の体に触れて・・・やがてその手は僕を持ちあげやさしくだいてくれた。小さいときにかあさんのふところに入っていたときのように・・・
・・・そうなのだ。ふとんの中でぼくは無意識に少しずつ上へ上へとのぼっていったらしいのだ。あたたかい手が僕の体に触れて・・・やがてその手は僕を持ちあげやさしくだいてくれた。小さいときにかあさんのふところに入っていたときのように・・・
ダヴィデは、ほうきをふりましてわめいていた。
あけ放されていたトイレに逃げこんだのが、最大のしっぱいだった。
「朝までトイレのなかでゆっくりしな。ここがてめえの寝室だ!」
再び電話がなりごそごそ話していたが、やがて僕をトイレに押しこめたまま、ダヴィデは出かけてしまったのだった。
僕はミャーミャー泣きさけんでいたけど、そんなことはむだなことだとはわかっていた。トイレの中を走ったり飛びあがったり、コップやビンをひっくり返したり大げさにやっていたけどそれもむだなことだってことも。いきなり下の方から、トントンとらんぼうにつっつく気はいがして太い男の声がどなった。
「いま何時だと思ってんだよっ!」
バスタブの中に、はみがきチューブのふたらしいのがころがっていたので、僕は気分てんかんにそれをころがして遊んでいた。そしてそれにも飽きてしまってバスタブから出て来て、よごれたしき布の上にまるくなって夜を明かしだのだった。
明け方、すっかりいい気分で鼻歌まじりでもどってきたダヴィデは、地震の後のようなトイレを見てぼうぜんとした。いっしょうけんめいいきさつを理解しようとしていたようだったけど、うずくまっている僕を見つけるや、その顔はざんこくきわまりない表情に変わった。