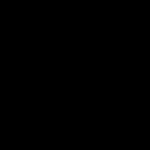「あ、おばあちゃんがよく鼻歌で歌ってる曲だね。鉄筆って、ガリガリいうの? だからガリ版?」
「そうさ。必死に鉄筆を動かしていたら、後ろで気配がするんだ。驚いて振り向くと、真っ黄色な服の若い娘が佇んでいた」
「誰?」
「こっちが聞きたいくらいだ。娘は無言で、仕事を手伝ってくれた。刷って、乾かして、綴じて」
「誰って聞かなかったの?」
「そりゃ、一度は聞いたさ。そうしたら、“月の子”だって答えたじゃないか。なるほど、満月の妖精のような清楚さだ。たぶん何か事情があって学校に来たのだろう、問い詰めてはいけない雰囲気だった。手伝ってくれるのは助かるから、二人で黙々と歌集を作った」

「妖精って本当にいるの? すごいな、おじいちゃん、妖精に会ったなんて」
「妖精は神々しいほど手際良かった。あっという間に歌集が完成して、ホッとしたよ。何より、二人で居ることがとても心地良かった」
「僕も会ってみたいな、妖精」
「しばらくして、また夜が遅くなった時に、学校の門の前で月の子に会った。その夜は月が出ていなかった。月の子も若葉色のカーディガンをはおり、まるきり普通の女性に見えた」
「二度も会ったの? 不思議だね」
「月の子は、学校の用務員室へ入っていく。そこには年老いた用務員さんがいて、月の子は鞄からお弁当を差し出した」
「お弁当? なんか、妖精らしくないね」
「それもそのはず。月の子は、実は用務員さんの娘で、遅い晩は夜ごはんを届けに来ていたんだ」
「なーんだ、普通の人だったのかぁ」
「その人は密かに私に惚れていてね。あの晩の手伝いは、彼女のアプローチ。まんまと騙されて・・・」
その時、ダイニングから、おばあちゃんの声が飛んできた。
「二人ともー! お食事が出来たわよ。冷めないうちに食べて」
僕が、
「はーい、今いくー!」
と返事をすると、おじいちゃんがクッと小さく笑った。
「月の子が呼んでいる。片付けは、ひとまずお終いにしよう」
(おわり)