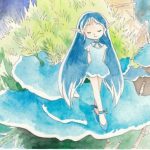運転手さん?
ああ、運転手さんにもそういう人がおありなのですね。
それは運転手さんがずっと一緒に過ごしてきた方ですか。
そうですか。そうですか・・・。
・・・・・・
もう、見えません。
本当につかのまでした。
流れ星のように一瞬でしたけれども妹はあそこに「いた」のでしょうね。
あの向こう岸に。
僕らがよく遊んだ、もう何百万年も前からここに流れている川の向こう岸に。
妹の身の上にたった今何かあったとしても、いえ、なかったとしても、妹の意識はもう「向こう」なのでしょうか。
林檎を持っていってやらなければ。
きっと待っています。
きょう一日の出来事や星の話や化石の話などをするのを楽しみに待っています。
そうだ。川のほとりを縁どっているあの野菊も摘んでいってやりましょう。
妹はうす紫色の野菊が好きだから。
そばに飾ってやりましょう。
 運転手さんは毎日毎日運転をしていて、今のように「向こう岸」が見えることがあるのですか。
運転手さんは毎日毎日運転をしていて、今のように「向こう岸」が見えることがあるのですか。
たまに?
ごくごくたまに?
あるのですね。
さっきみたいなことが。
きっと何度も何度も同じ風景を見ていると、その中のわずかな違いやずれに、気づくのでしょうね。
そしてこのバスが、いったいどこへ向かって走っているのかわからなくなってしまうことが? まれにあるのですって?
さっき僕は行き先がいつもわかっているのはすごいことだなんて感心したのですけれども、あるのですね。そういうことが。
決められた目的地に向かうことを繰り返していると、時にそんな風に感じるものなのでしょうか。
それも今の景色のようにほんの一瞬だけ、思うことなのですね。
ごくたまに運転手さんに見えるという「あの場所」には、いったい何があるのでしょう。
手の届きそうな向こう岸なのに、すぐに渡っていけそうな川向こうなのに、ずいぶんと遠い遠いところのような気がします。
何時間、何日、バスを運転し続けても、決して着くことはない場所のような――
僕はもう学校を辞めてしまったので、これまでのように毎日決められた時間に、というわけにはいかないと思いますが、病院に行ったり、山の向こうの町に苗や種を買い付けに行ったりするので、時々はバスに乗らせてもらいます。
またお会いできるでしょうか。
そろそろ停留所が近づいてきました。
僕は次で降ります。
運転中に僕のおかしなひとりごとを聞いてくださって、申し訳ないことでした。
ええ、そうです。あの北の空に光っているのが「北極星」です。
旅人の目印の星です。〈了〉
(初出「日本児童文学」2010年11・12月号。本作は「新作の嵐」掲載にあたり推敲したものです)