「君も高く飛べた時には、海を見たことがあるでしょ? 海の見える方角が東。その反対の方角が西だよ」
「ああ、日が沈んで行く方角が西だね」
「そうそう。それで、海を左に見て、夕日を右にした時、頭の向く方角が南なんだ。だから、南西っていうのは、頭と右のつばさの間の方向さ」
「そうか!」
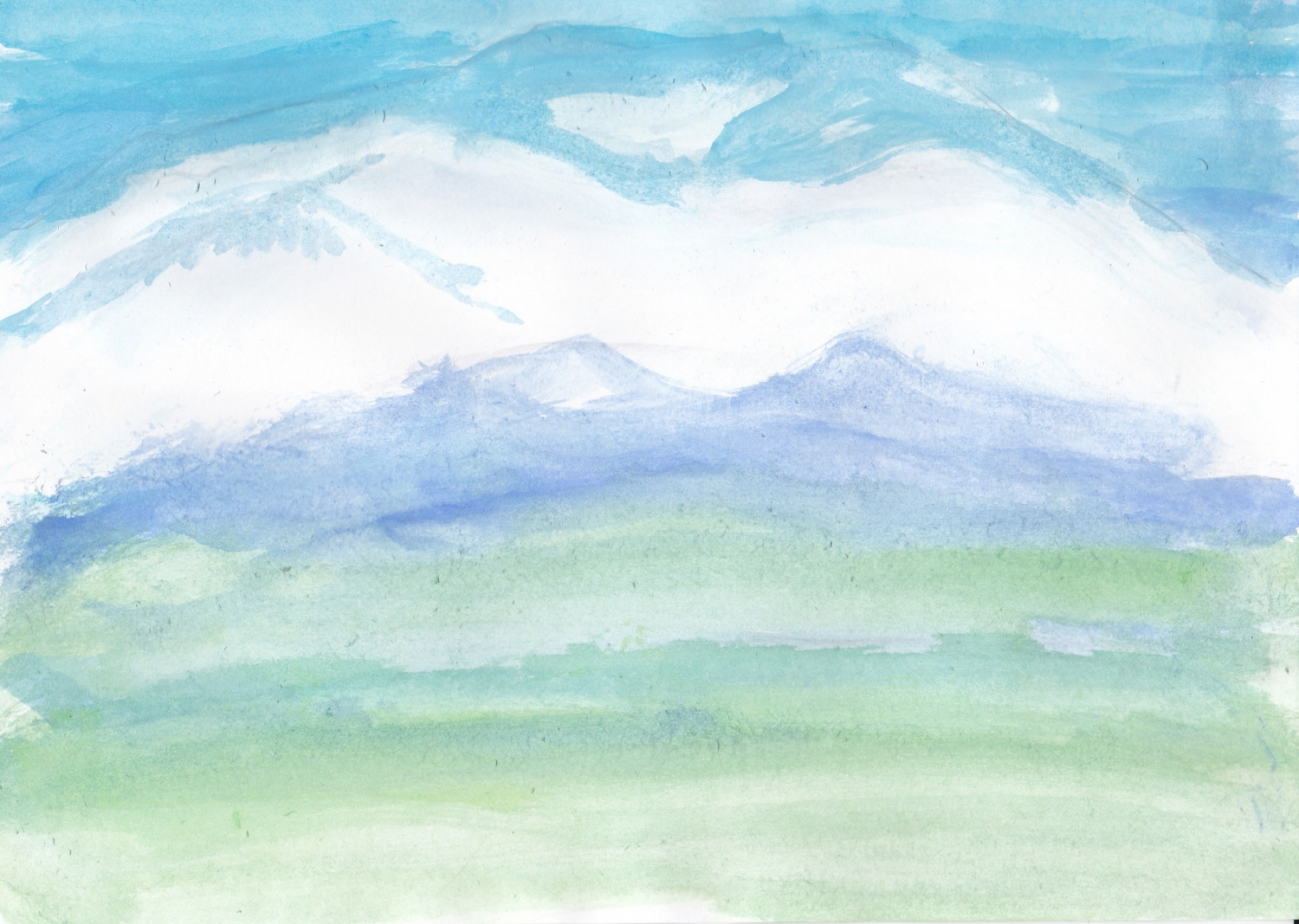 ハトはピンと来ました。
ハトはピンと来ました。
まだ、とても元気だったころ、ビルの間を吹き上がる風に乗って、仲間といっしょに、町で一番高いビルまでも、楽々と、飛んで行ったものでした。
その時には、家々が、ぺったり、立ち並ぶ、だだっ広い平野の先に、確かに海が見えました。
出ていく船や、入ってくる船。せん回するたび、上がったり、下がったりする水平線。
反対方向に目をやれば、こんもりした森の上に、雲と混じり合うようにして、遠い山々がありました。
冬、とりわけ寒い晴れた日には、青空を背に、すき通るような白い姿が、くっきり、横たわっていたものです。
「あの一つが蔵王だったんだ」
「そこまでなら、君だって行けると思うし、太陽王に会えると思う」
「ありがとう! 行ってみるよ! 君には何てお礼を言ったらいいか!」
ハトは、何度も、ポポッ、ポポポッと、頭を下げました。
「でもね、オイボレ君、君は、ほんとうに、それでいいの?」
チェシャが、ためらいがちに、聞きました。
「太陽王がどんな鳥にせよ、君は、やっぱり、食べられちゃうんだよ。それだったら、ここで、のんきに暮らした方がよくはない? 仲間がいじめるんだったら、ぼくが、毎日、ここに来て、守ってあげたっていい。そうだ、いっそのこと、ヨハンソンさんのところにおいでよ。動物好きの、とてもやさしい人だから、君のことだって、きっと、最後まで、めんどうを見てくれるよ」
「それで、立派なおそう式をしてもらって、お墓に入るのかい?」
ハトは顔を上げて、明るい日差しの中で針のように細くなっているネコの目を、まっすぐ、のぞきこみました。












