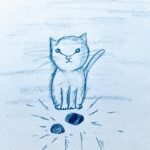ピイ、ピイ、ピイ――。
ハッとした。それは間ちがえようもないほどに、聞き知った声だった。黒々とした木々の合間から鳴き声が聞こえるのだ。
「ピイ! いるのか! 帰ってこい」
よびかけるとすんだ声が返ってきた。
確信を持った。あれは、絶対にピイだ。
秋斗(あきと)を追いかけて来たお母さんがかたに手をかける。
「秋斗、残念だけどもうすぐ夜だしムリだよ。家に――」
「お母さん、あの声、ピイだよ! エサ、ほしがってる」
「そっか。秋斗にはわかるのか・・・。けど、一度外に出た鳥はむずかしいな。明日一日は、目立つところにエサを置いてみようか。まだ巣立つには、ちょっと早すぎる日数だと思うから。もどってこれるといいけど」
その日の秋斗は生きた心地がしなかった。父のなぐさめにもうなだれたまま、タオルケットをかぶって真っ暗な部屋の中で、ただピイの無事だけをいのった。
寒くないだろうか。夜行性の肉食の生き物にやられたりしないだろうか。
まんじりともしないまま夜が明けると、秋斗は一目散に庭のウッドデッキにかけ出した。
「ピイ!」
うらの林に向けて、よびかけた時だった。