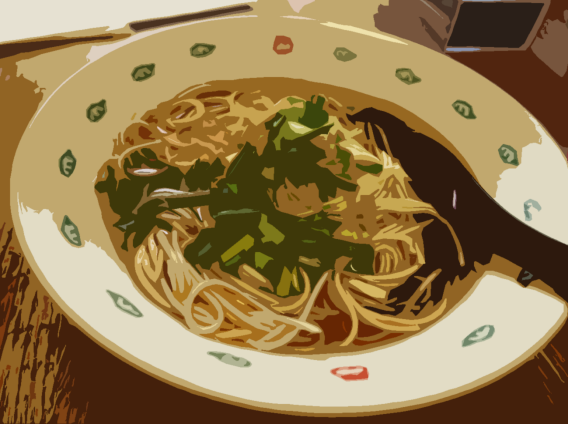「黒岩、おまえ、今日は、仕事じゃなかったのか? 幸太、おまえ、こんなところで、なにをしている?」
大きな声を発しながら、姿を現したのは、猿神さんだ。
「先輩こそ、どうしてここに?」
「ワシは、いろいろ忙しくてな。家の裏のばあさんから、次の依頼主を紹介され、そのじいさんから、また次のばあさんを、うーっ、思い出すのも面倒だ! 要するに次々仕事を依頼されたんだ! 人手が欲しいと、家に電話をかけても、だれもでない。いまも次の仕事に向かう途中だ。そこで、」
そこまで一気にまくしたてると、
「ふいっ、ふいっ、ふいっ」
猿神さんが、苦しみだした。
「だ、大丈夫ですか? いや、大丈夫なはずがありませんよね! 黒岩さん、救急車を呼びましょう!」
「あわてなくていい、幸太くん。救急車は必要ないんだ」
のんびりと構える黒岩さんの横で、猿神さんは、息を乱して苦しんでいる。
「やはり、しましょう、119」
「大丈夫。猿神先輩は、ほくそ笑んでいるだけだから」
「そ、そうなんですか?」
と見れば、発作はおさまってきたようだ。
「そこでだな、黒岩、おまえのラヴちゃんを発見したわけだ。さあ、おまえたち、こんなところで、ふたりでつるんでないで、ワシの仕事を手伝うがいい。・・・ああ、チャッピーは黒岩の車の中で休んでいてね」
なるほど、そういうことなのか。
少し、ホッ。
それに、猿神さんの乱入のおかげだろうか、空気がちょっと明るくなった。
「猿神さん、仕事は手伝います。でも、少し、待ってください」
とにかく、山野辺さんをなんとかするのが先だ。
「いやだ! ワシ、待つの、きらいだ!」
猿神さんが、足を踏みならす。
「なんですか、それ! 先輩は、子どもですか!」
「黒岩、おまえは、バカか? このワシが幼気な子どもに見えるのか?」
「まさか! 先輩がかわいかったり、いじらしかったりするはずないじゃないですか! 言葉のアヤってもんです。それに、先輩、バカと言う奴がバカなんです!」
「ふん、バカと言う奴がバカと言う奴の方が、もっとバカ!」
空気は明るくなったけど、ついていけない。
それに、ついていきたくも、ない。
けれど、ぼくは、ピンときた。
名探偵の猿神さんなら、もしかしたら解決の糸口を見つけてくれるかも・・・。
この人は、『猫アンテナ』という特殊な能力さえも、するんと受け入れてしまえるような人でもあるし。
危険でデリカシーがなくてバカだけど、懐は深いのかもしれない。