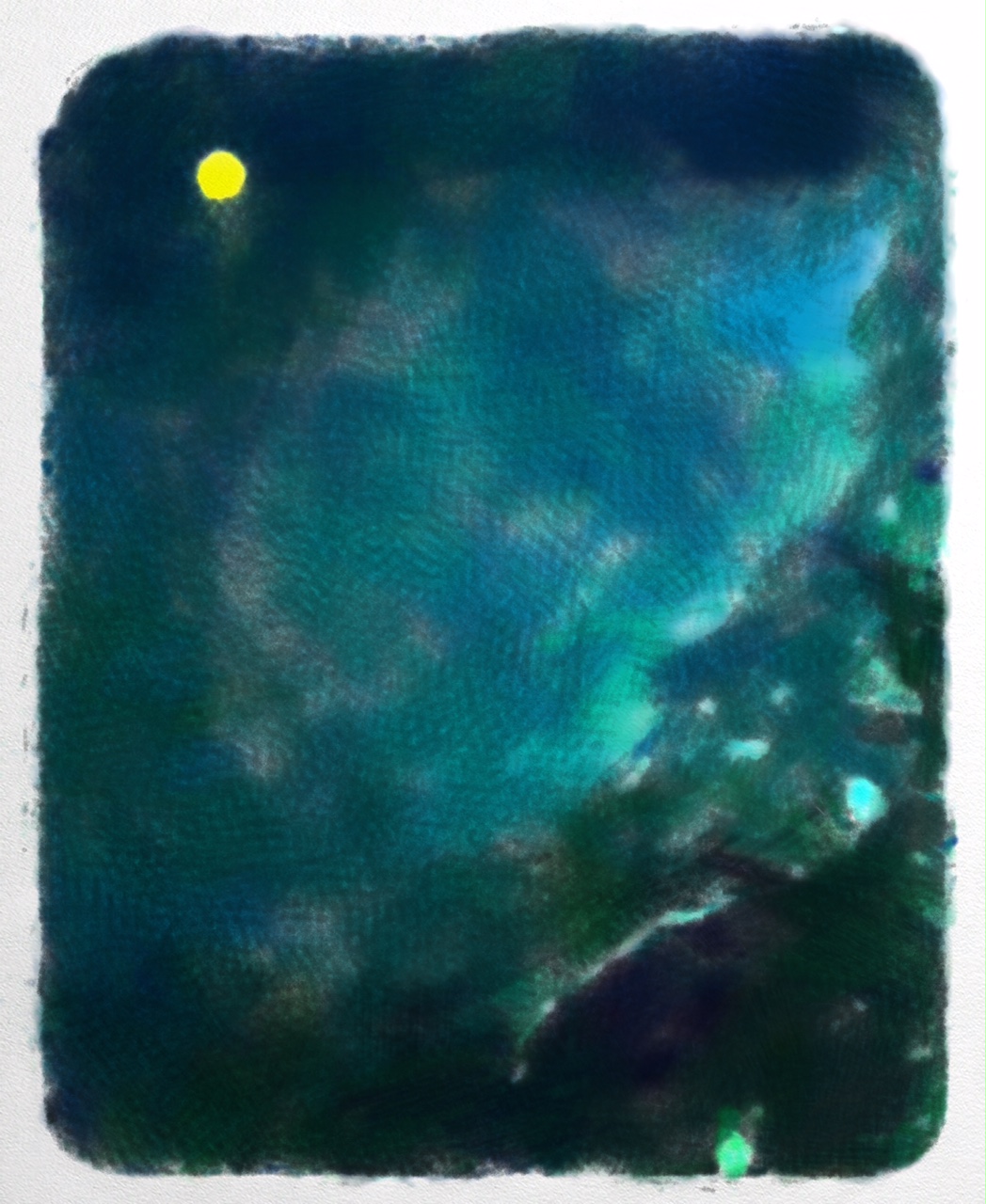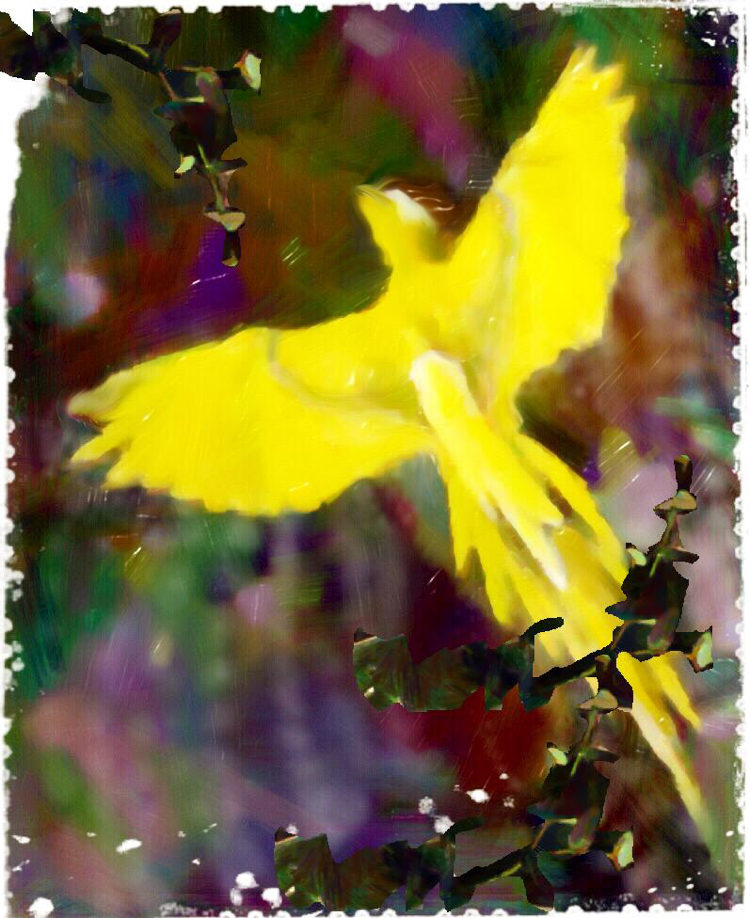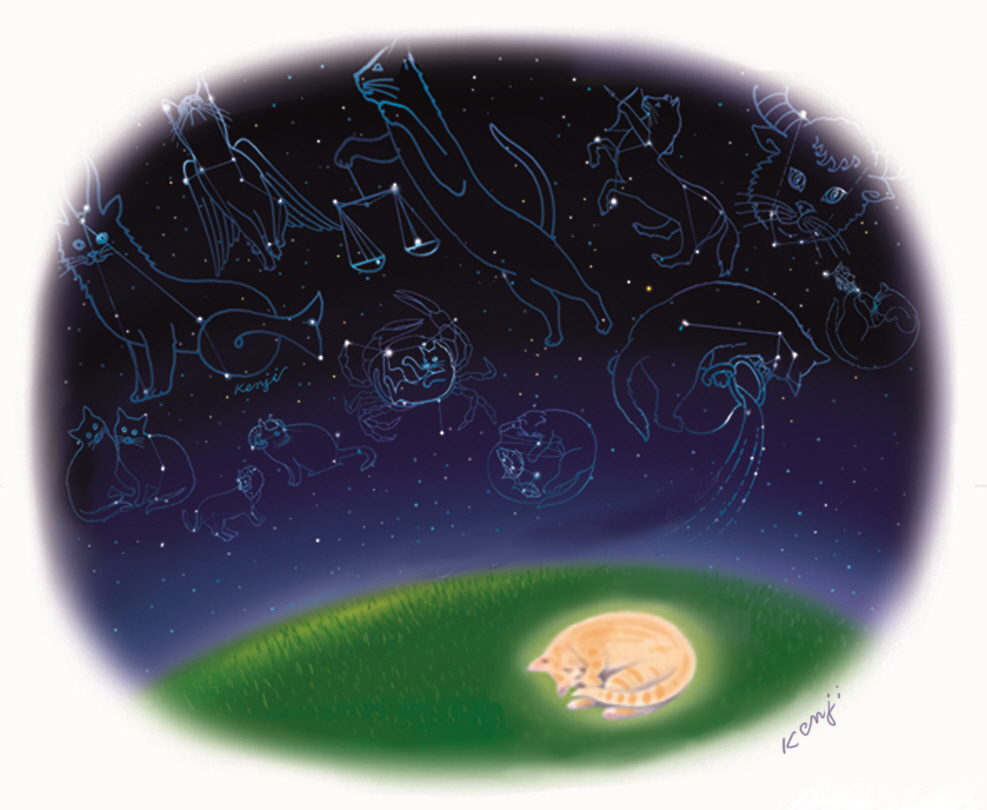スゥはゆっくり深呼吸をすると、湖の涙を、ゴクゴク、ゴクゴクと飲み始めました。
そして、ひび割れて石のように硬くなった幹の皮を、歯を食いしばって引きはがし、力をふりしぼって枝を持ち上げ、精一杯空に向かってのばして、重たい雲を夢中でかき分けました。
すると、陽の光に触れた毒のきりは少しずつ晴れて、実にも赤い色が少しずつ戻りはじめました。
スゥは枝をしなやかに伸ばして女の子を優しく抱き上げました。
そして、実に穴を開け、その果汁を女の子の口に運ぶと、みるみる肌のつやが良くなり、女の子が元気を取り戻しました。
「さあ、早く帰って、この実を食べさせてあげなさい」
スゥは自分のツタでくつを編んで女の子にはかせ、大きくみずみずしい実をひとつ渡しました。
「うん!」
女の子は笑顔でこたえ、渡された実を両手で大切にかかえると、走って戻っていきました。
スゥは倒れていた周りの人たちにも枝で実を運ぶと、ひとり、またひとりと、立ち上がりました。
やがて、街の人々も戻ってきました。
王様もお城の人々も戻ってきました。
みんなに笑顔が戻り、 みんながスゥに感謝を伝えました。
大切なものをもう二度と傷つけないために、スゥは再び空に向かってどんどん大きくなっていきました。
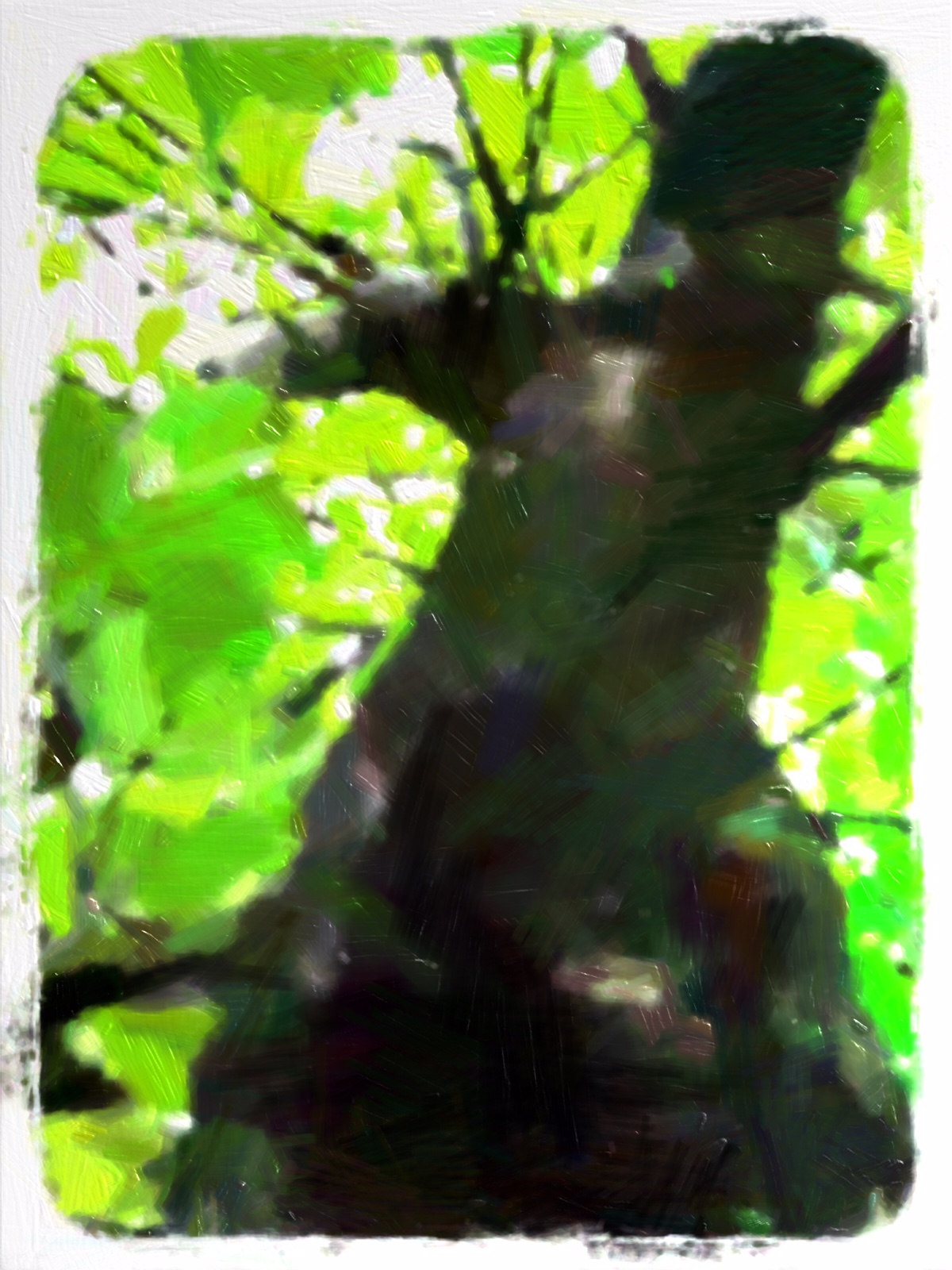 そして月日は流れ、世界のどこからでも見られるほどに大きく成長したスゥは、何があっても枯れることなく、いつしか「世界樹」と呼ばれ、たくさんの人からしたわれました。
そして月日は流れ、世界のどこからでも見られるほどに大きく成長したスゥは、何があっても枯れることなく、いつしか「世界樹」と呼ばれ、たくさんの人からしたわれました。
その年の最後の冬の嵐が通り過ぎた、おだやかなある日のこと。
「心地の良い枝に美味しい実。ずっとここにいたいね」
目をやると、枝の上に並んで羽を休めている、ライラと雄鳥とかわいい子供たちの姿がそこにありました。
まだ少し冷たい風から彼女たちを守ろうと、スゥは気付かれない様にそっと葉をよせました。
一瞬、風にゆれる枝と葉のざわめきの中で、
「ありがとうね、スゥ」
と、大好きなあの声が、聞こえた気がしました。