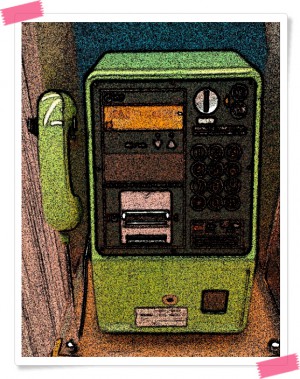ぼくはベッドのはしっこのところに丸くなってよこたわった。
〈今夜ひとばんだけここに寝かせてくれよね〉
たった1週間前までそうしていたのに、まるでそれが1年前のことのようだ。ステッラがぼくを見つけたらどうするだろうか。息の根がとまるまでぶつかもしれない。それとも雪の中に放り出すかもしれない。もうどっちだってかまわない。このまま死んでしまえば本望というところさ。とにかくねむい。たたき起こすなら、最後のお願いだ、8時間あとにしてくれよね・・・。
 あれ? ぼくは、またまたウエディングドレスの前にいるんだ。ハーッとキバをむきだして、ぼくの一番得意のおっかない顔をしてみせる。だのに白いドレスの女はにっこり笑っているのだ。意外! 顔がまともにくっついている。きゃーっ、お化けっ! 女はさっとすくうようにぼくを抱きあげる。
あれ? ぼくは、またまたウエディングドレスの前にいるんだ。ハーッとキバをむきだして、ぼくの一番得意のおっかない顔をしてみせる。だのに白いドレスの女はにっこり笑っているのだ。意外! 顔がまともにくっついている。きゃーっ、お化けっ! 女はさっとすくうようにぼくを抱きあげる。
「まあ、マーポったら、どうしたのよ? あたしよ」
ステッラなのだ、助けてぇ・・・。ぼくは彼女のうでの中から飛びだすと、どんどん走り出した。明るいみどりの野原を。ステッラは白いドレスを蝶のようになびかせながら、おっかけて来る。もう走れないよ。ぼくが雑草の中にひっくりかえったとき、ふわふわした白いものが体をおおった・・・。
窓から冬の太陽がいっぱいにさし込んでいた。
「あ、眼をさましたみたいだ」
「あら、本当だわ。ときどき、変な声だしてたけど、夢を見てたのかもね」
「よっぽど疲れていたんだね。もう昼近くだよ。」
男と女の顔が心配そうにぼくを覗きこんでいた。
「マーポ。よく帰ってきたわねぇ。とっても心配してたのよ」
二人の顔が間近にあり、笑っているのだ。ステッラの目になみだが光っている。夢を見てるのだろうか。それとも天国にいるのだろうか。
ステッラはぼくを抱きあげた。
「マーポったら、こんなにやせてしまって・・・食うや食わずだったのね。ダヴィデから電話があって、マーポが出て行ってしまったなんて言うんだもの。あたし心配で心配でごはんものどに通らなかったのよ。でも、マーポはきっと帰ってくるって思ってた。とっても頭がいいから35キロの道だって絶対大丈夫だって。あたし、毎日教会に行ってお祈りしてきたけど、神様が聞いてくださったのね。あらまあ、耳のところが血が出てるけど、またけんかしたの?」
「やっぱりマーポにはこの家が一番いいんだよな、そうだろう? これで楽しいクリスマスが迎えられるね。マーポももう子供じゃあないんだから、あんまりおいたをするんじゃないぞ」
ぼくも少しはいたずらがへって、ひがみ根性も影をひそめてきたみたいだし、ステッラもあまりヒステリーではなくなった。つまり,お互いに年とともにいくらか成長したってわけ。
「こいつ、またサロンに入り込んでいるぞ」
「かまわないわよ,布の肌ざわりがとってもすきみたい。あんなに気持ちよさそうにねむってるわ」
山とつまれた布の上に身をうずめてうたたねするって、とっても気持ちがいいんだ。ざらざらした触感が最高だ。ジーンズって、夏は涼しく冬は暖かいってきいてたけど、ほんとうだと思うよ。
ステッラは『椿姫』をききながら、たまにはいっしょに歌ったりしながら、ミシンでズボンにファスナーをぬいつけることによねんがない。
さらば過ぎし日よ・・・
悲しい歌なのに、ちっとも悲しげでなく口ずさんでいる。
「おい、『ブルースカイ・ジーンズ』のロッシから電話だ。どうする?」
「またぁ? るすだと言って。あの男,なまじっか電話にでると、1時間もまくしたてるんだから。あの口にファスナーをぬいつけて、しゅーっとしめてやりたいくらいよ」これでお分かりだと思う。ステッラは神経をすりへらされるウエディング・ドレスの内職をやめて、ジーンズにファスナーをつけるという新しい内職にかえたのだ。こんなことになったのも、ちょっぴりぼくの責任でもあるんだけれど。
もうけはどうだって? さあ,アパートを買うまでにはまだまだ時間がかかりそうだけどね。