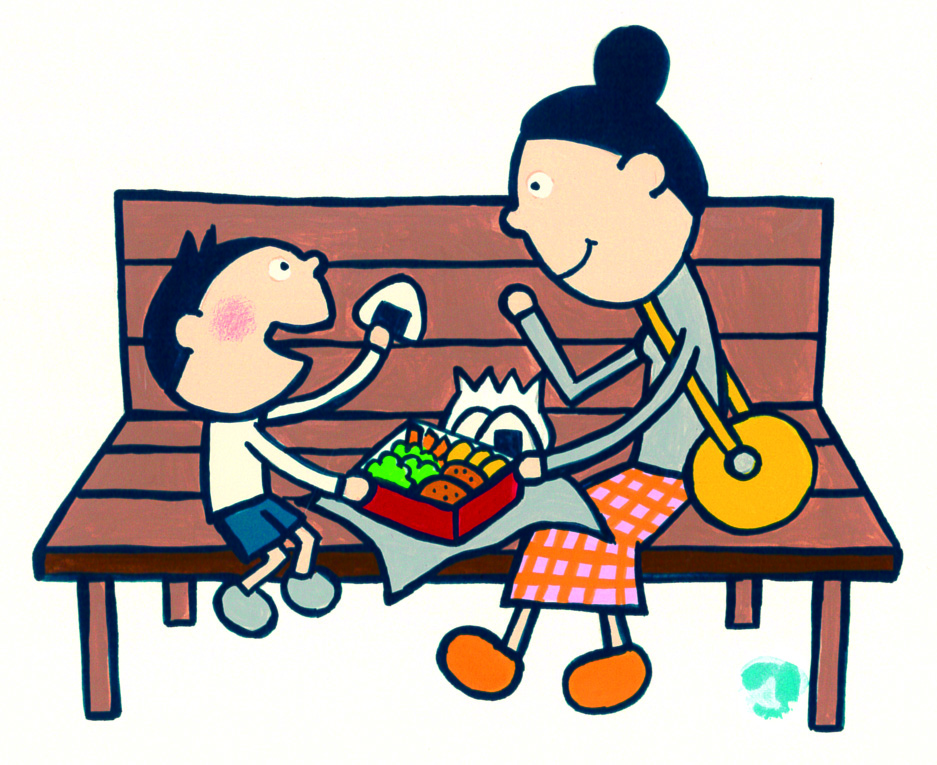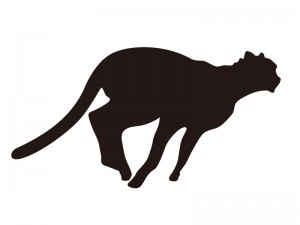中庭には行かなかったけれど、ぼくはやよいさんのことが心配で、何度か近くまで行ったこともあります。
半年たったころには、やよいさんのかなしみは、少しうすらいだようでした。
ある時、ぼくは、家の中がバタバタとそうぞうしくなり、部屋の中にダンボールがつまれていくのに気がついたのです。
《もしかしたら、やよいさんは、おひっこしするのかな》
明日がやよいさんのおひっこしという日のことです。
ぼくは、さいごのあいさつをしに行くことにしました。
どうしても、やよいさんに、今までのお礼が言いたかったし、「元気にくらしています」ということもつたえたかったのです。
やよいさんは、近所のお姉さんと立ち話をしていました。
「これまでいろいろお世話になりました。ひっこすといっても、それほど遠くはないから、また遊びにいらしてね」
やよいさんがお姉さんに、そう話しているときに、ぼくはその横をゆっくり通りすぎました。
やよいさんは、すぐにぼくだとわかってくれました。
でも、そのお姉さんが、あんまりネコがすきじゃないことを知っているので、はっとした顔はしたものの、それまで通りお姉さんと話をしながら、だまってぼくにしせんを送ってくれました。
「今まで、ありがとうございました。ぼくは元気でやっています。だから安心して、おひっこししてください」
そうニャア、ニャア言って、ぴんと立てたシッポを3回ふりました。
 やよいさんにもその言葉はとどいたようで、ほっとした様子でした。
やよいさんにもその言葉はとどいたようで、ほっとした様子でした。
そして同時にさびしそうな顔もしました。
「さようなら、やよいさん。やよいさんもお幸せに!」
ぼくは、もう一度、やよいさんに大きくシッポをふって、後ろをふり向かず、歩いて行きました。