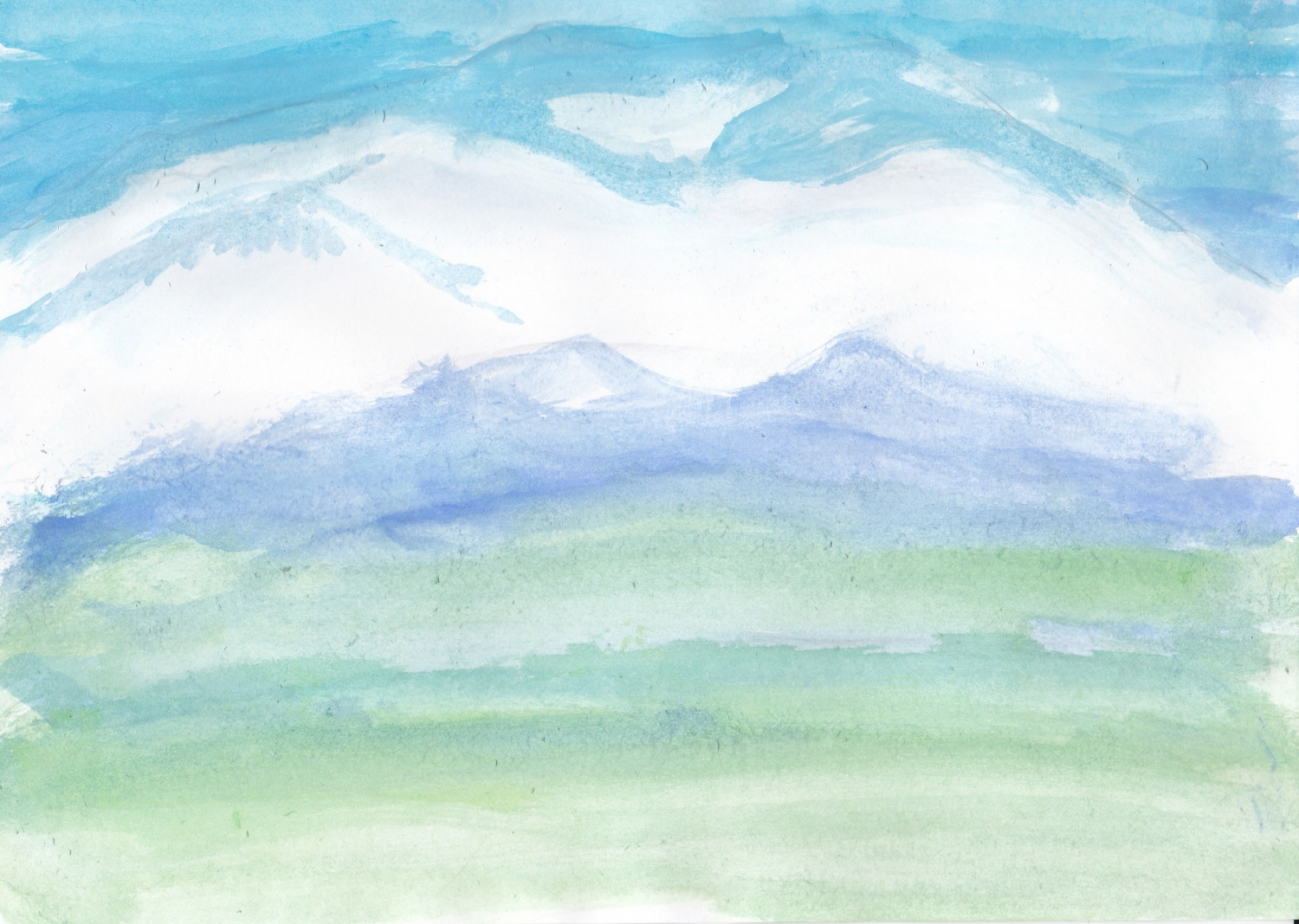村上春樹
『海辺のカフカ』
◆あらすじ◆
ギリシャ神話や日本の古典を絡め、時間を超えた不思議な出会いの物語。主人公田村カフカは中野区で高名な彫刻家の父と二人で暮らしていた。が、15歳の誕生日、父の呪いから逃れるために、四国へ家出。辿り着いた私設図書館の職員と知り合い、図書館暮らしを始める。
 その頃、中野区では、戦時中に謎の失神を体験した知的障害の老人ナカタさんによって、カフカの父が刺殺される事件が起きていた。ありえないことに、父が殺された時間、カフカの手には、自分が父を刺したような返り血が。さらに現実とは信じがたいが、図書館館長の美しい女性・佐伯さんが15歳当時のままの様子で、カフカの部屋に現れるようになる。
その頃、中野区では、戦時中に謎の失神を体験した知的障害の老人ナカタさんによって、カフカの父が刺殺される事件が起きていた。ありえないことに、父が殺された時間、カフカの手には、自分が父を刺したような返り血が。さらに現実とは信じがたいが、図書館館長の美しい女性・佐伯さんが15歳当時のままの様子で、カフカの部屋に現れるようになる。
佐伯さんは、30年前に大ヒットを生み出したシンガーという華やかな過去と、自分の片割れのような恋人を若くして亡くしたという悲しい過去を抱えながら、ひっそりと生きていた。カフカには「この人こそ、僕を捨てた母かもしれない」と思えてきた。