7 ペナルティゲーム
足が、がくがく、ふるえます。
「助けをよばなくちゃ!」
美里ははうように玄関ホールまでもどり、声をしぼり出しました。
「だれか助けて!」
ホールはがらんとしていて、人の気配はまるでありません。
美里は自動ドアをぬけ、うらしま館から外に出ました。
来た時と同じ、おだやかな海の景色です。
ところが、向こう岸までの道は、とっくに、海水に飲みこまれていました。
「ああ、どうしよう! そうだ、ガイドさん!」
美里はうらしま館にかけもどり、受付のタブレットに飛びつきました。
プィン!
「何かご用ですか?」
「大変なんです! 大介君が水そうにさらわれました! 弟も行方不明です! どうしたらいいんですか!」
「大介様は、今、ペナルティゲームの最中です」
「ペナルティ?」
「はい、第三問をおまちがえになったので。ご様子をごらんになりたければ、大介様のアバターをおしてください」
「大ちゃんのアバター?」
「画面の右方に・・・」
なるほど、画面の片すみに美里、大介、新一のイラストが並んでいます。
美里は大介のアバターをおしました。
ガイドの顔が消えて、代わりに、水中でもがいている大介のすがたが映りました。
「おぼれてる! 何とかして!」
「では、道具をお選びください」
すると、画面に道具のイラストが並びました。
おにぎり、かいちゅうでんとう、アクアラング。
「アクアラング!」
ピコピコピン!
水中に本物のアクアラングやダイビングスーツが現れて、大介を包みました。
とたんに、大介は楽そうにおよぎ出しました。


 「どっちにせよ、おれたち、入れないや。お金、ないもん」
「どっちにせよ、おれたち、入れないや。お金、ないもん」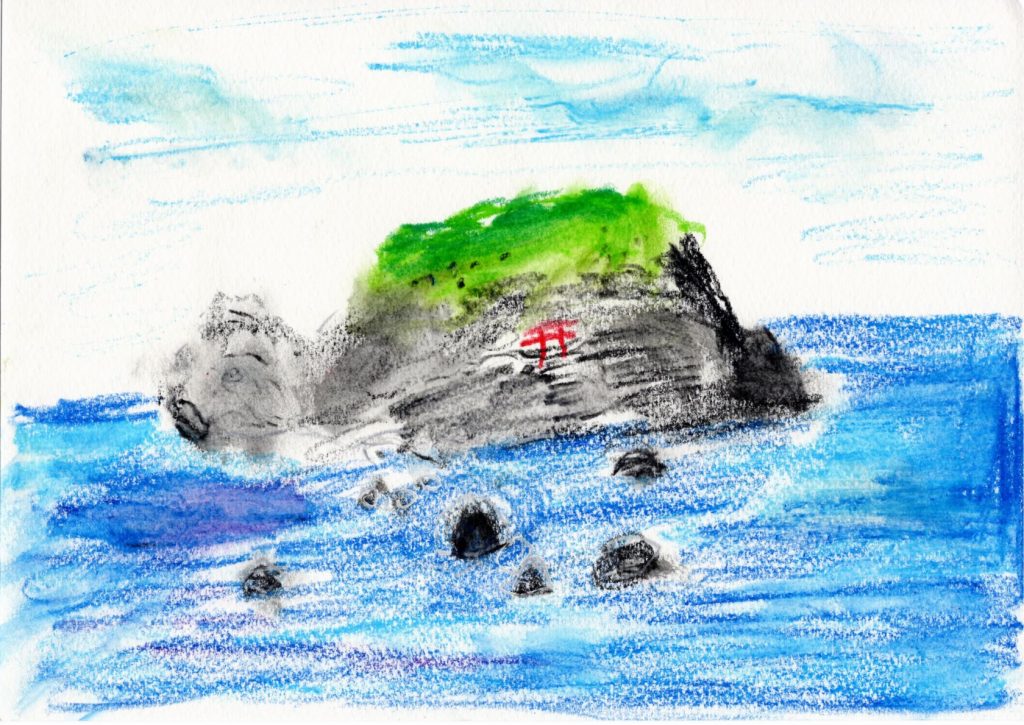



 おじいさんはふたたび、駅の窓口に行きました。
おじいさんはふたたび、駅の窓口に行きました。




